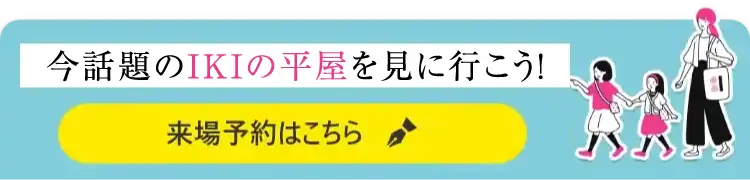平屋の歴史を知る、いつから2階建てが主流になったのか?

日本の住宅は長らく平屋が中心でしたが、いつから2階建てが主流になったのでしょうか。歴史的な背景や都市化、住宅政策の影響を解説し、現代における平屋人気の再燃についても紹介します。「日本の家」と聞くと、庭付きの平屋をイメージする方も多いでしょう。実際、戦前までは平屋が一般的な住宅様式でした。しかし、高度経済成長期以降は2階建てが圧倒的に主流となり、平屋は少数派に。では、なぜこの変化が起きたのでしょうか。本記事では、平屋から2階建てへと移行した歴史を振り返ります。
≪目次≫
平屋が一般的だった時代
江戸〜昭和初期

庶民の住まいは基本的に平屋が中心でした。理由は、木造建築の耐震・耐火性能の制約と、農村部における広い敷地確保が容易だったためです。
武家屋敷や商家では2階建てもありましたが、庶民住宅は「平屋+屋根裏部屋」程度が主流でした。
戦後と住宅不足

第二次世界大戦後、都市部では深刻な住宅不足が発生しました。狭い土地に効率的に住まいを供給するため、2階建て住宅の建築が増え始めます。
高度経済成長と2階建て主流化
1960年代〜1970年代

都市への人口集中が進み、宅地が狭小化。限られた敷地を有効活用するため、2階建て住宅が標準となりました。
住宅メーカーによるプレハブ住宅の普及や住宅金融公庫の制度も、2階建ての建築を後押ししました。
2階建てが定着した理由

都市部の土地価格高騰
少ない土地でも延床面積を確保できる二階建ては高騰する土地価格に対応する有効な手段でした。限られた土地の中で、いかに効率よい家を作るかが課題となり普及が進んでいきます。
世帯人数の多さ
高度経済成長期に伴い大幅な人口増が発生いたしました。大家族に対応するため狭い土地の中で部屋数を増やす必要が出てきたことから二階建てが一般的となったと推測されます。
法制度の影響
二階建てが定着した理由の中で、建築基準法などの法律が整備されたことも要因の一つです。建ぺい率・容積率の制約の中で効率的に広さを確保する方法として2階建てが有利だったと言えます。
平屋人気の再燃

〇近年、平屋人気が再び高まっています。
〇高齢化社会でのバリアフリー需要
〇核家族化・少人数世帯の増加
ZEHや高断熱住宅の普及により、光熱費の課題を解決できるようになった
「平屋=贅沢」というイメージも浸透し、郊外や地方を中心に再評価が進んでいます。
まとめ
日本の住宅史において、長らく平屋が当たり前でしたが、戦後の住宅不足と都市化によって2階建てが主流に。
しかし現代では再び平屋が注目を集め、時代ごとの暮らし方や社会背景に合わせて住宅のあり方は変化してきました。
IKIは日本の歴史を大事にしつつ、今に進化した平屋を展開しております。二階建て、三階建てが主流となっている現代ではありますが、平屋の需要は広がっており、改めて平屋の良さを多くの方に伝えていきたいとコストを抑えながら幅広い地域に展開しています。モデルルームや店舗も随時増えておりますので、近隣の店舗がございましたら是非一度ご相談してみて下さい。
平屋の間取りを見たい方はこちら⇓⇓⇓⇓⇓
間取りを確認する
IKIは規格型の平屋住宅です。間取りは100種類以上ございますので、
詳しい間取りプランを御覧になりたい方は、資料請求がおすすめです⇓⇓⇓⇓
資料請求をする
IKIなら実際に平屋を見学することもできます。
実際にIKIを見たいという方はこちら⇓⇓⇓⇓⇓
来場予約をする